はじめに|捨てられないもの、どうしてますか?
「使ってないけど、まだ使えるし…」
「いつか使うかもしれないし…」
こんなふうに迷って、捨てるでもなく、とっておくでもなく、しまいこんだままになっている物たち、ありませんか?
それを解決してくれるのが、「保留ボックス」という考え方です。
今回は、“もったいない”を大事にしつつ、物を減らせる方法として、
誰でも今日から始められる「保留ボックス活用法」をご紹介します。
1. 「捨てられない」の多くは「判断できない」だけ
捨てられない人がよく言う理由には、こんなものがあります。
- もらいものだから
- 高かったから
- まだ使えるから
- 思い出があるから
でも本当のところは、「今使っているか、必要か」に答えられないだけ。
つまり、判断を後回しにしている状態なんです。
2. 「保留ボックス」とは?
✔ 定義
「いまは使っていないけど、すぐには捨てられない物」を一時的に入れておく箱やスペースのこと。
✔ ポイント
- 捨てるわけじゃない → 精神的ハードルが下がる
- “いつまでもそこにある”を防ぐために期限を決める
- 定期的に見直すルールをつくる
3. 実際にどうやって作るの?
ステップ①|箱・カゴ・袋を用意する
- 無印の収納ボックスや、ダンボールでOK
- 「保留」とわかるようにラベリング
リンク
ステップ②|ルールを決める
- 保留期間:1ヶ月〜3ヶ月程度
- 見直し日をカレンダーに書く(スマホアラームでもOK)
ステップ③|何を入れる?
例:
- 数ヶ月着ていない服
- なんとなく取ってある空き瓶・紙袋
- 使わないけど高かった雑貨
ステップ④|見直すタイミングで判断
- 使わなかったら → 手放す(捨てる or 譲る)
- 思い出系なら → 写真を撮ってデジタル保存も選択肢
2,3か月に一回は中身を確認するようにしましょう
4. 「保留ボックス」があると暮らしがこう変わる
✅ 迷う時間が減る
→「とりあえず保留ボックスに入れよう」が選択肢になる
✅ 無理に捨てなくて済む
→「罪悪感」が減り、継続的に物を減らせる
✅ 持ち物に向き合えるようになる
→ 「本当に必要か」を、時間をおいて客観視できる
5. 応用編:家族や子どもにも使える
- 子どもの「遊ばないけど捨てられないおもちゃ」
- パートナーの「着てないけど文句を言われそうな服」
→ まずは保留ボックスに入れて提案してみましょう。
意外と、1ヶ月後には忘れていることも。
まとめ|“いつか使うかも”から卒業する
| 状況 | 解決策 |
|---|---|
| 捨てられない | 判断を保留ボックスにゆだねる |
| 捨てたくない | とりあえず保留、期限をつける |
| モノが減らない | 自分の選ぶ力を育てる習慣を |
「保留ボックス」は、**今すぐ全部を決めなくていい“優しい片づけ方”**です。
暮らしの中で、判断できる力は少しずつ育っていきます。
焦らず、でも少しずつ。モノとの関係を整えていきましょう。
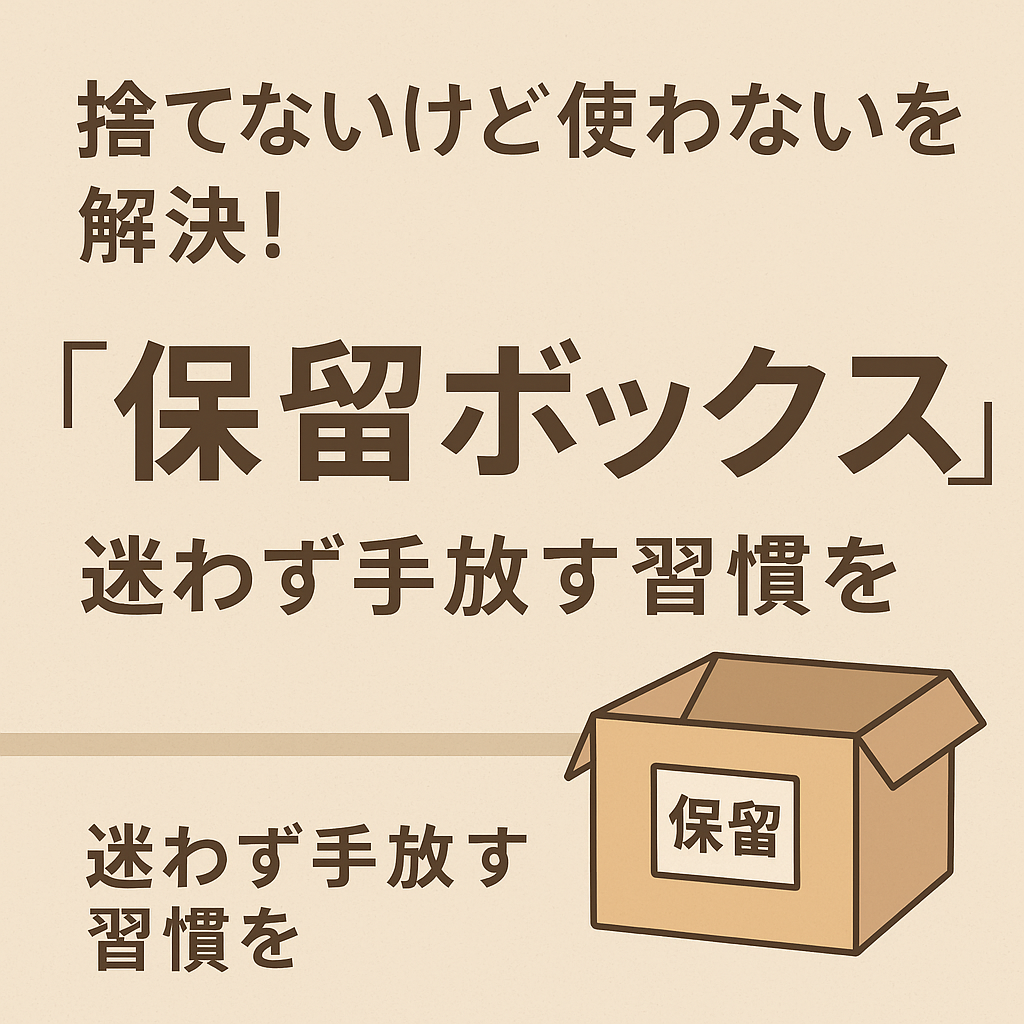
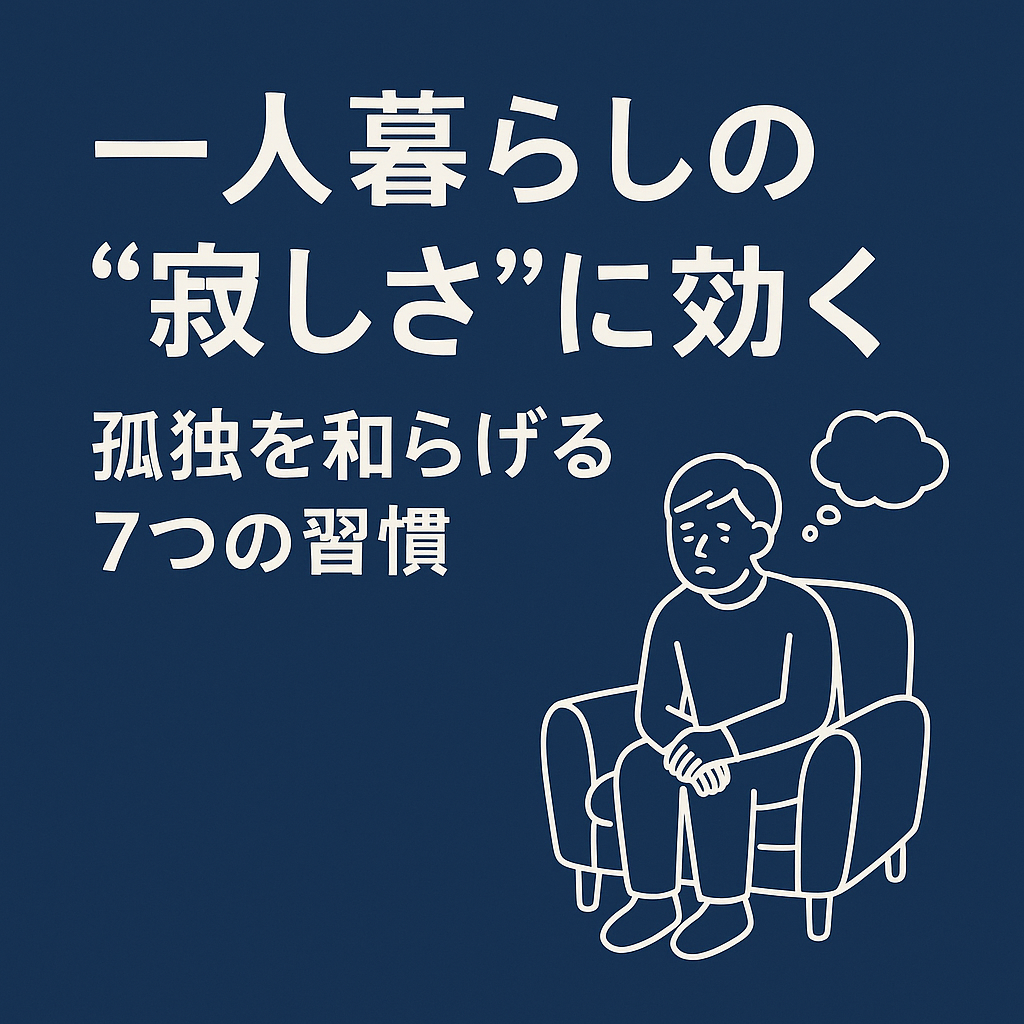

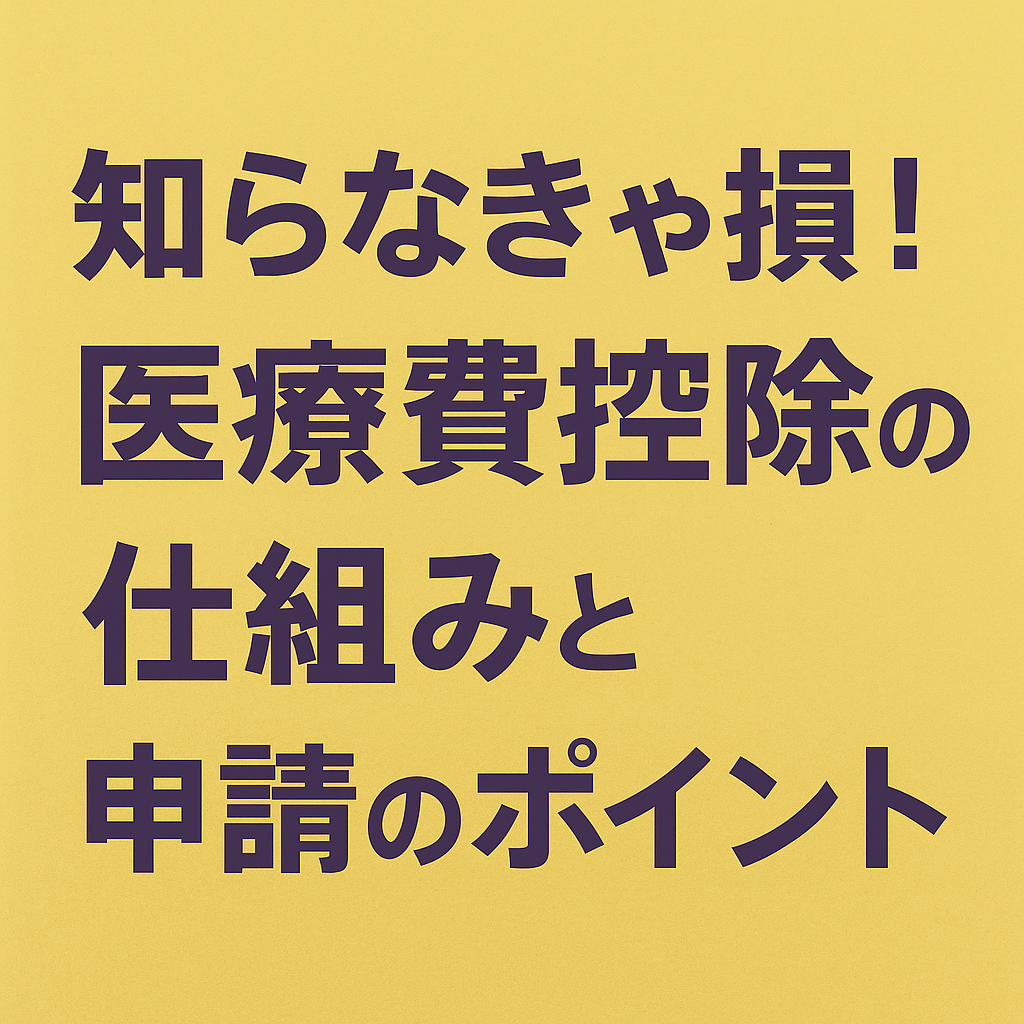
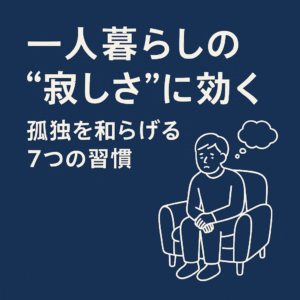
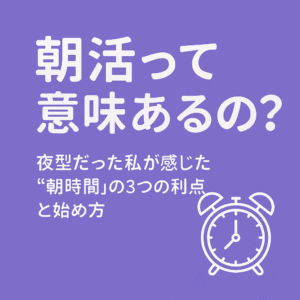



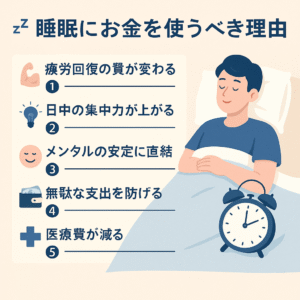


コメント