🏡 予備って、結局どれくらい必要?
- 壊れたときのために取ってあるマグカップ
- 使ってないけど「予備」として置いてあるハンガー
- 新しいのを買ったあとも残っている古い布団
「いつか使うかも」で持ち続けている“予備のモノ”、ありませんか?
この記事では、「備えること」と「ためこむこと」の境界線を見直し、
予備をムダにせず、スッキリ暮らすための考え方をご紹介します。
🔍 なぜ「予備」が増えるのか?
- 不安:「壊れたら困るかも」
- 罪悪感:「まだ使えるのに捨てたらもったいない」
- 思い出:「前に使ってたものだから手放しにくい」
どれもよくある感情。でも実際は…
✅ 「予備」と言いつつ、実は“使う予定のないもの”を置いているだけのことも。
📦 本当に“予備”として機能してる?
以下のようなチェックをしてみましょう:
- 使った記憶があるか?(半年以内)
- 使う場面が想像できるか?
- 今すぐ壊れても、本当にそれを使うか?
👀 「とりあえず取ってあるだけ」のモノは、“予備”ではなく“保留品”かもしれません。
🧠 予備を手放しても後悔しない考え方(改訂版)
- 「使えるか」ではなく「使うか」で判断
- 手放しても買い直せるかで判断(例:100均のタッパーなど)
- “予備”の数は1つまでと決める
- 半年使っていないものは“今後も使わない”可能性が高いと考える
⏳「半年」をひとつの目安にすると、判断がブレにくくなります。
💡 予備を持つなら、ルールを決めて
- 予備をしまう“箱”を1つだけ決める
- 中身を季節ごとに見直す
- “1軍に昇格”しないものは手放す
📦 収納スペースがあふれたときは、「予備品を持ちすぎてないか」を疑ってみると◎。
予備はそれ専用の箱に入れる、テープを貼っておくなどで分かりやすくし、半年そのままだったら捨てちゃいましょう。
リンク
リンク
📝 まとめ|「念のため」は無限に増える
| 状況例 | 判断基準 |
|---|---|
| ハンガー10本中3本は使ってない | 2本予備にして、1本は処分 |
| マグカップが6個ある(1人暮らし) | 2個+1個予備でOK |
| 古いスマホが3台ある | SIMが入る1台だけ残す |
🗂 あとがき
“もったいない”という感覚は大事です。
でも、「なんのために持っているのか」が曖昧なまま予備を増やすと、かえって暮らしにストレスが増えます。
予備と向き合うことで、持ちすぎない・ためこまない暮らしが、少しずつ整っていきますよ。
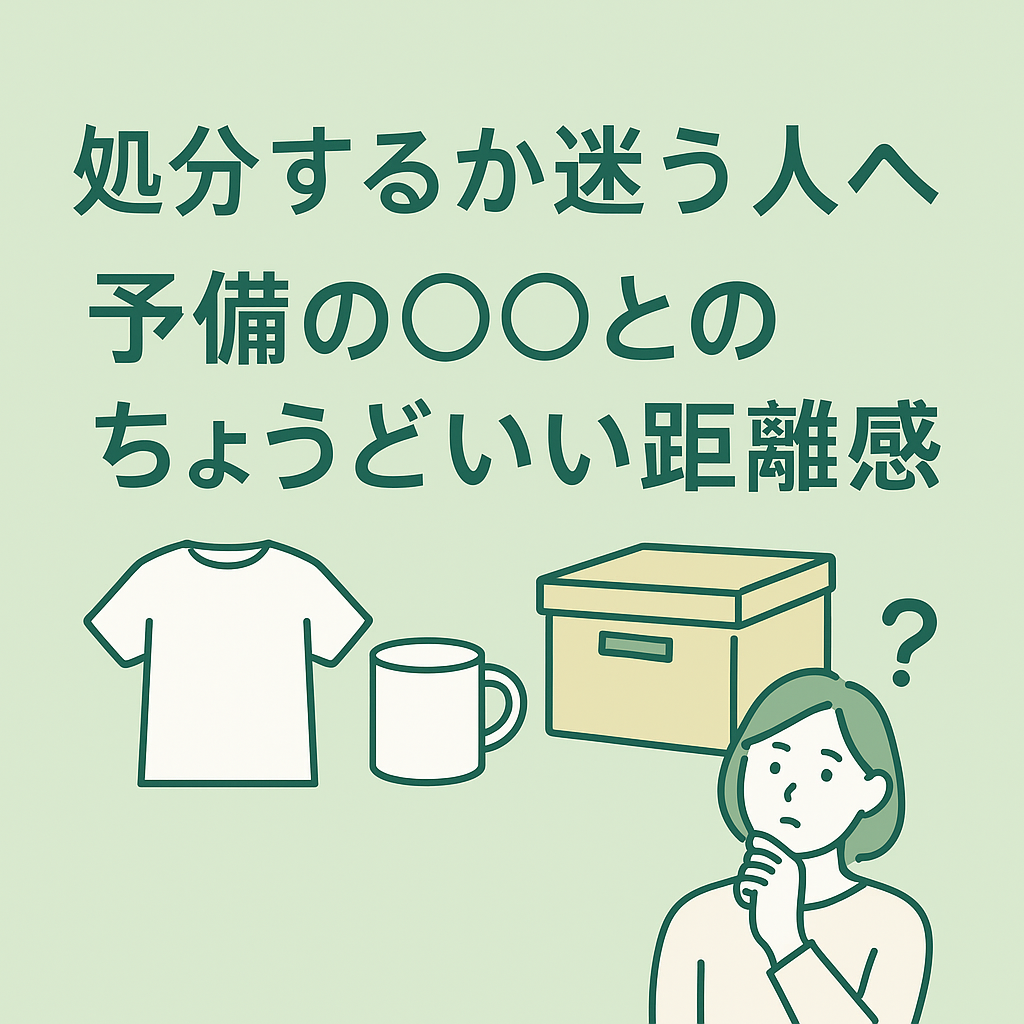
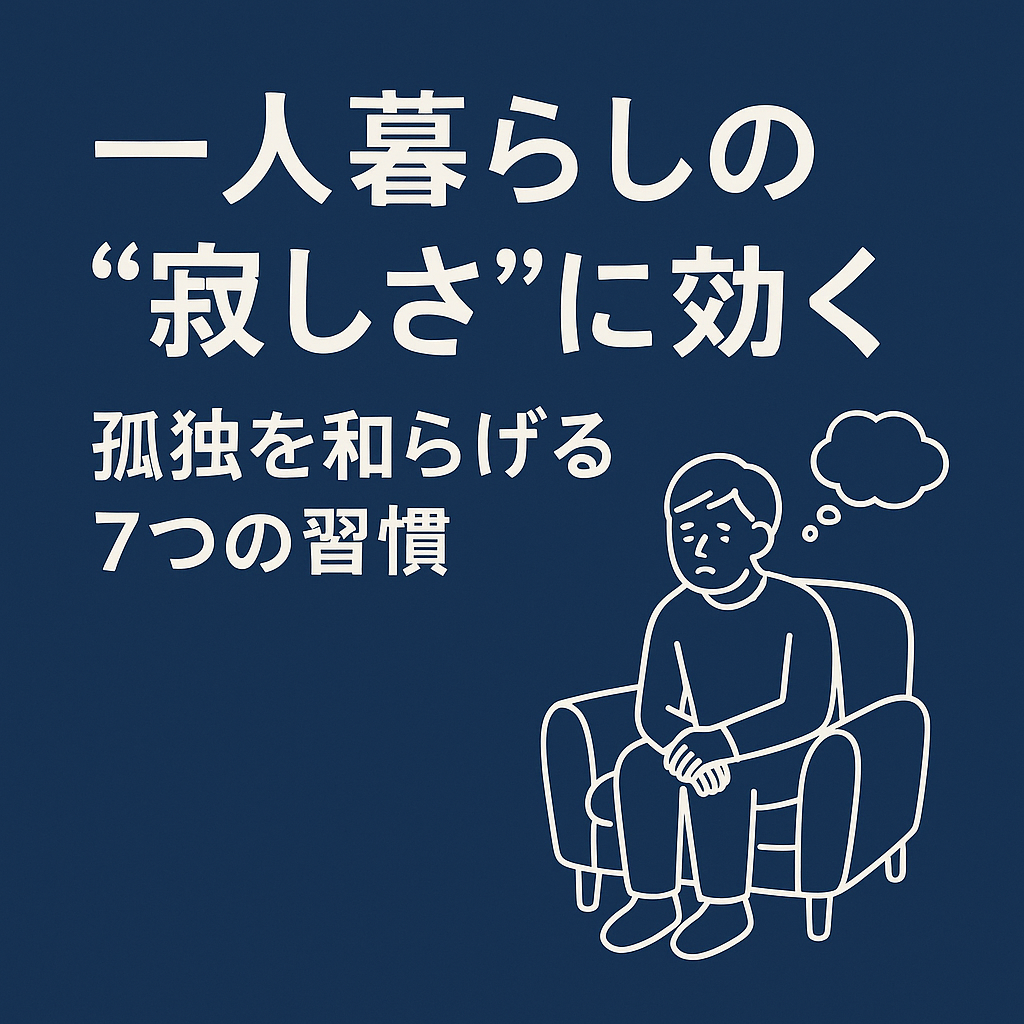

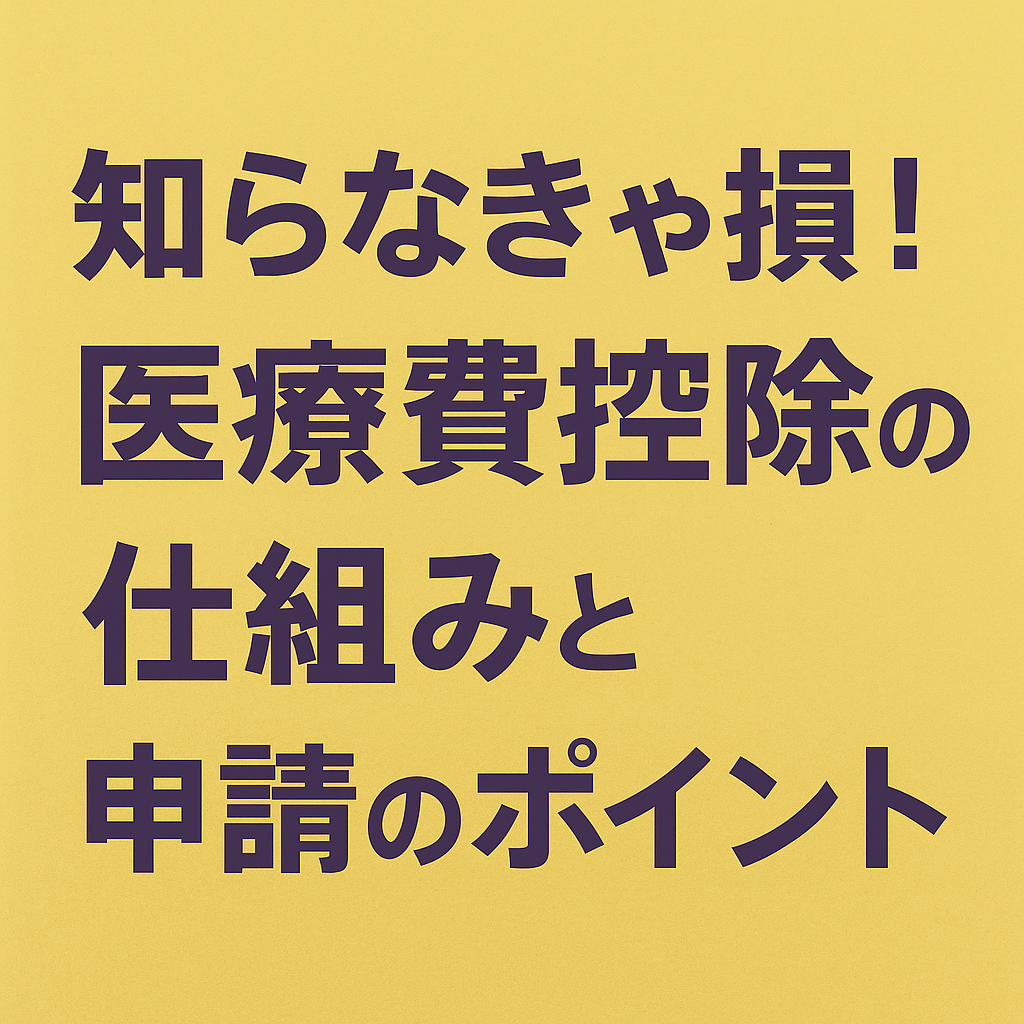
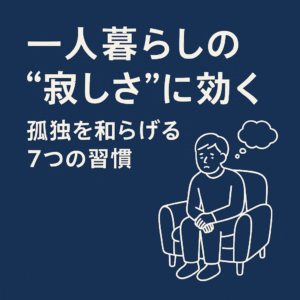
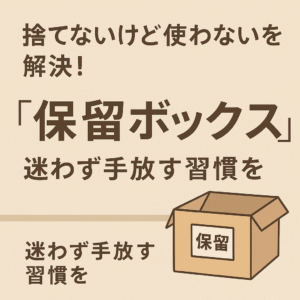
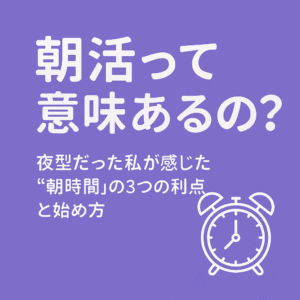



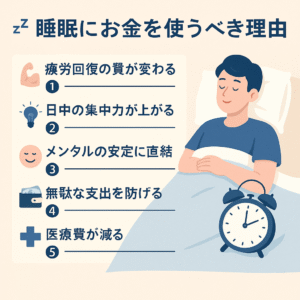

コメント