はじめに
「安かったから買ったのに、すぐ壊れて使えなくなった…」
「結局買い直す羽目になって、最初からちゃんとした物を買えばよかった」
そんな“安物買いの銭失い”を経験したことはありませんか?
この記事では、安物買いのループから抜け出すための視点と、具体的な判断基準をわかりやすく紹介します。節約志向の方や、限られた予算で良い買い物をしたい方にこそ読んでほしい内容です。
なぜ「安物買いの銭失い」が起きるのか?
多くの人が、「とりあえず安いもの」で済まそうとするのは自然な心理です。
しかし、この選択が逆にお金も時間も無駄にする原因になることもあります。
理由はシンプル。
「その商品の“総コスト”を見ていないから」です。
たとえば:
- 500円の傘を年に3本壊す → 合計1,500円
- 2,000円の耐風傘を3年使う → 年666円
最初に安い方を選んでも、結果的には高くつくことが多いのです。
判断に迷ったときのたった1つの基準
→ 「1回あたりいくらか?」で考える
どういうこと?
高いか安いかの判断を「購入価格」だけでなく、
**使用回数で割った“1回あたりのコスト”**で見るのです。
たとえば:
- 安い靴(2,000円):半年で劣化、週3回使用 → 約33円/回
- 高品質な靴(8,000円):3年間使える、同じく週3回使用 → 約5円/回
一見高く見えても、高品質な方が圧倒的にコスパが良いとわかります。
安物買いをしてしまいやすい3つのパターン
1. 「今すぐ必要」で焦って買う
→ 急いでいると比較検討の時間が取れず、安さだけで決めがち。
2. 「とりあえずこれでいいか」で済ませる
→ 自分の不満やストレスに気づかず、買い替えを繰り返す悪循環。
3. 「話題・レビュー数」に惑わされる
→ 高評価でも価格相応の品質しかないことも。自分の使用頻度と合っているかが重要。
逆に、初期投資を惜しまず買ってよかった例
以下は筆者の一人暮らし生活で「高かったけど買って正解だった」ものの例です。
| 商品名 | 初期費用 | 使用頻度 | 使用年数 | 1回あたりのコスト |
|---|---|---|---|---|
| 鉄フライパン | 3,500円 | 週5回 | 5年目 | 約2.6円 |
| バスタオル(今治) | 2,000円 | 毎日 | 3年目 | 約1.8円 |
| 折りたたみ傘(耐風) | 2,500円 | 月3回 | 5年目 | 約13円 |
「長く使えるか」「ストレスを減らしてくれるか」で選ぶと、結果的に満足度が高くなります。
補足 実際に筆者が使っているやつ
上の例はAIが作成したものであり、フライパンはニトリの26cmの深底のもの、折りたたみ傘は学生時代から使っているいくらかわからないやつ、タオルはふるさと納税で10枚入り12000円くらいのものを使っています。
高いけど買ってよかったものTOP3はドラム式洗濯機、食洗器、スマートロックproですが、この3つはそもそも高い買い物になりますね……
安物買い的な観点だと、マットレスや枕あたりは安物を買わず、そこそこお金をかけて良かったと思っています。
逆に洗剤やラップなどは安いものでも問題ない気がします。
予算が限られている人はどうする?
高いものを買えばいい…わけではありません。大切なのは**「自分にとって本当に必要かどうか」**。
✅判断のポイントは以下の3つ:
- どれくらいの頻度で使うか?(週1?毎日?)
- 壊れたとき、買い直すコストと手間は?
- 安いものを使い続けた場合の“総コスト”は?
この3つを考えるだけで、“安物買い”はグッと減らせます。
まとめ:高いか安いかではなく、「納得できる買い物」か
- 「安物買いの銭失い」を避けるには、使用頻度 × 耐久性 × 使い心地で判断するのがコツ。
- 「高くても1回あたりのコストが安い」ものは、実はとても節約的。
- 焦らず、調べて、「自分に合う」ものを選ぶ習慣をつけよう。
おわりに
本当の節約とは、「安く買う」ことではなく、「無駄に買い直さない」こと。
次に何かを買うとき、
「これは長く使えるか?」「安くても買い直すことにならないか?」
そんな問いかけを1つ加えるだけで、後悔のない買い物ができますよ。
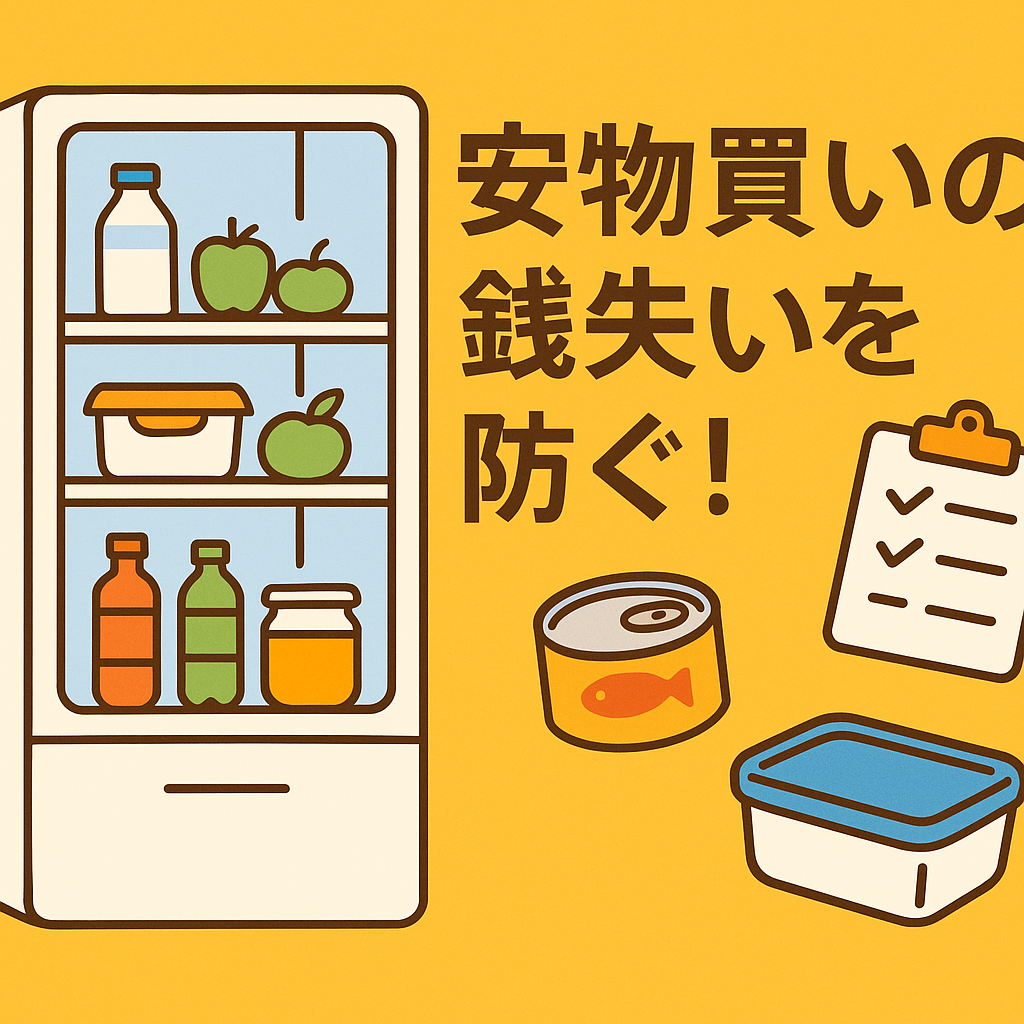
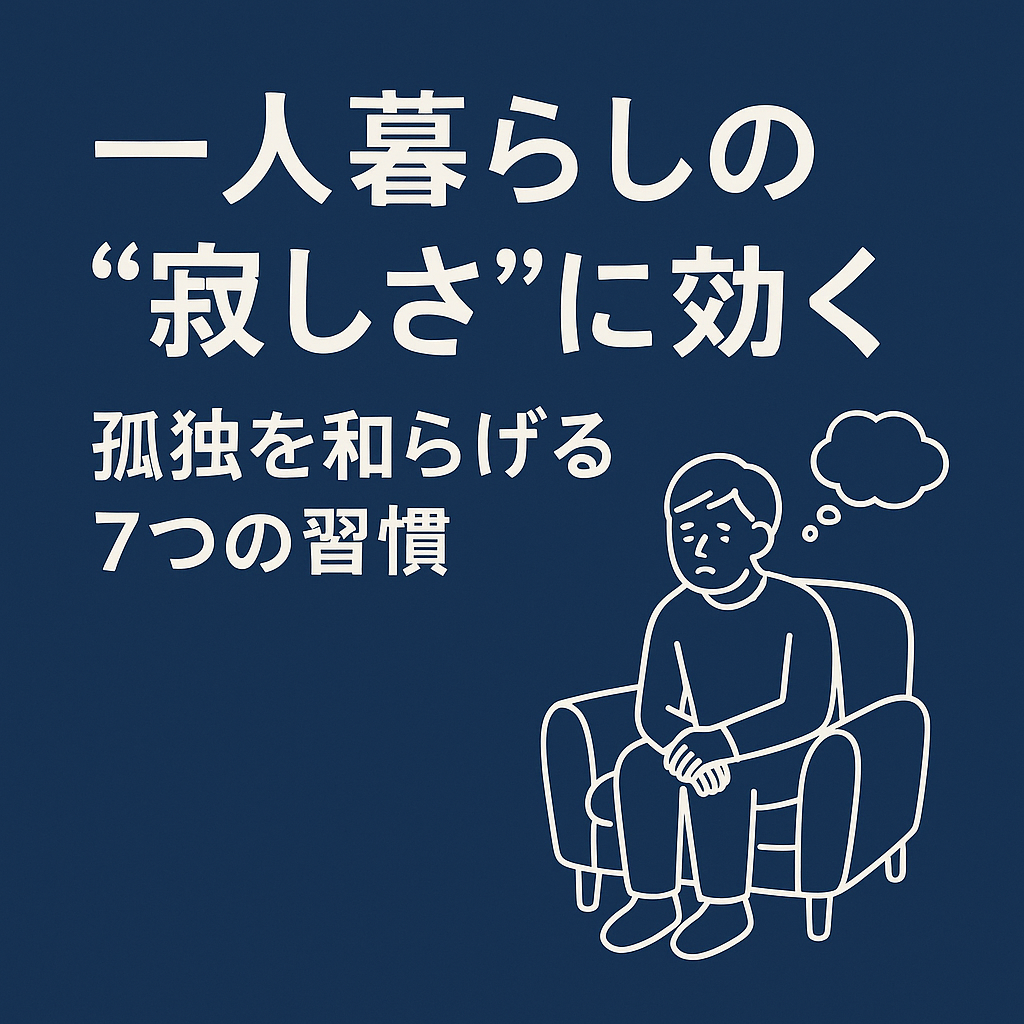

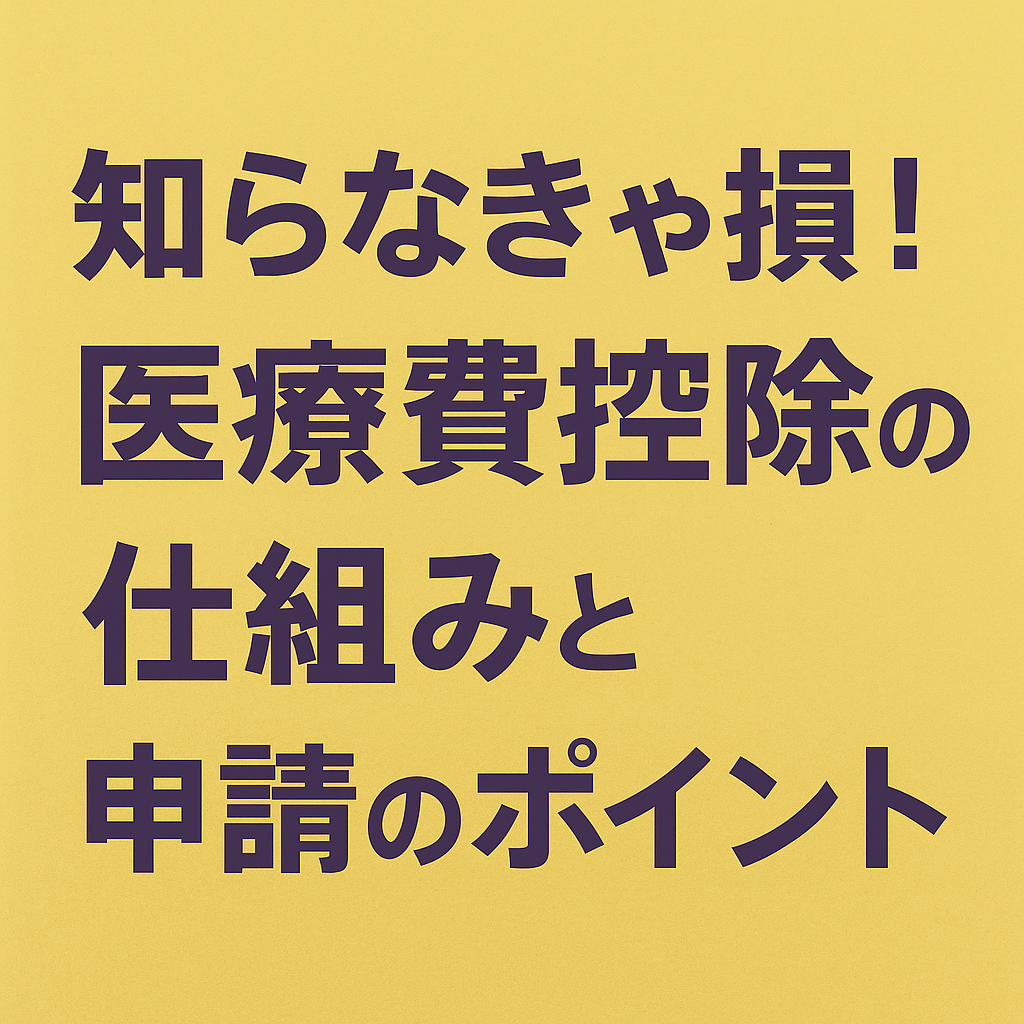
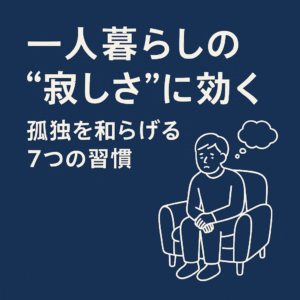
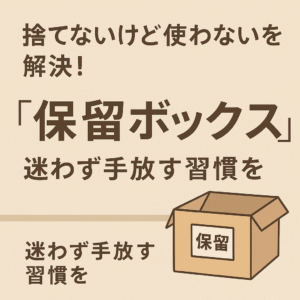
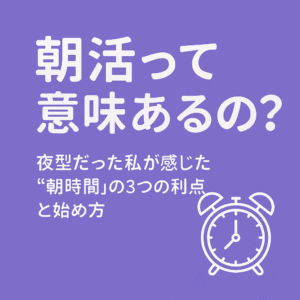



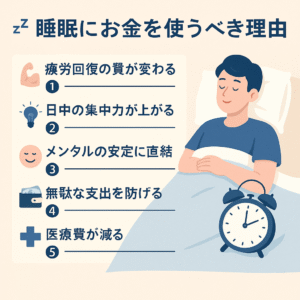

コメント